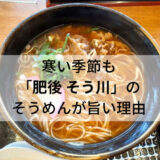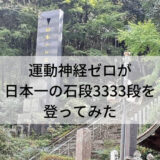沖縄の夏を彩る勇壮な伝統芸能、エイサー。
最近では全国放送のテレビで取り上げられたり、沖縄県外にも多くの団体が設立されたりと、その知名度は着実に向上しています。沖縄を飛び出し、内地で大規模な祭りが開催されることも珍しくなく、毎年7月の最終土曜日に開催される新宿エイサーまつりは特に有名です。
しかし、「太鼓を叩きながら踊る盆踊り」というイメージはあっても、「一体いつから始まったの?」「どんな意味があるの?」といった歴史や由来は意外と知られていません。
この記事では、エイサーの歴史と特徴をわかりやすく解説する入門ガイドとして、起源や歴史、太鼓の種類などをご紹介します。読み終える頃には、エイサーに対する見方が変わり、次に鑑賞する際の感動が格段に深まるはずです。
- エイサーの起源や歴史
- エイサーで使用される太鼓の種類について
- エイサーの種類について
この記事は沖縄生活13年、エイサーサークルに所属し一万人のエイサー踊り隊や新宿エイサーまつりに出演したことのあるももとが書いています。
\楽天トラベルなら楽天ポイントが貯まります/
\沖縄の宿を予約する/
(公式サイトに移動します)
目次
エイサーの歴史をわかりやすく!起源や由来

沖縄の伝統芸能エイサーの起源は、現在の勇壮な踊りからは想像もつかない、意外な歴史を持っています。
エイサーのルーツを語る上で欠かせないのが、江戸時代初期に活躍した袋中上人(たいちゅうしょうにん)というお坊さんです。なんとこのお坊さんがエイサーを始めた人と言われています。
袋中上人が琉球にもたらしたもの
袋中上人は、浄土教を布教するため、1603年に琉球(現在の沖縄)へ渡りました。
現在の沖縄では仏教のイメージは薄いかもしれませんが、琉球王朝時代には本土から多くの仏教文化が伝来していました。その名残は、首里城にある「万国津梁の鐘」にも見ることができます。あの大きな釣り鐘も、当時の琉球に仏教が深く浸透していたことの証です。
琉球に渡った袋中上人は、当時の国王である尚寧王(しょうねいおう)にも認められ、布教活動を行います。
彼は仏教の教えとして念仏を広めました。この念仏が、時を経て念仏歌としてエイサーの歌の中に受け継がれ、時代とともに形を変えて現在のエイサーになったと言われています。
そのため、エイサーは別名「念仏踊り」と呼ばれることもあるのです。
エイサーが「盆踊り」になった理由
エイサーが沖縄の盆踊りとして定着したのは、以下のような信仰の流れがあったからです。
念仏→先祖供養→盆踊り(念仏踊り)
つまり、エイサーは単なるお祭り騒ぎではなく、ご先祖様の霊を送迎し供養するための大切な精霊踊りとして始まったのです。
ちなみに、袋中上人が建立に関わったとされる袋中寺は、現在も那覇市小禄の住宅街に残っています。興味のある方は、ぜひ訪れてみてください。
沖縄全島エイサーまつりの歴史

沖縄全島エイサーまつりは、1956年(昭和31年)に「全島エイサーコンクール」として、戦後の沖縄市(旧コザ市)で始まりました。
米軍統治下で混乱していた時期、地域の青年たちの交流と沖縄文化の復興を願って、各地の青年会エイサーを一堂に集めて競い合う形式でスタート。このコンクール形式により、「見せるエイサー」としての魅力が高まり、沖縄最大の夏の風物詩へと発展しました。
1977年に「沖縄全島エイサーまつり」と改称し、現在はコンクール形式ではなく祭りのスタイルとして、30万人以上が訪れる一大イベントになっています。
ちょんだらー(京太郎)の歴史
チョンダラーは、エイサー隊を率いる道化師(どうけし)役です。
その歴史は古く、本土から来た門付け芸人や、念仏者(ニンブチャー)の要素が融合したと考えられています。漢字では「京太郎」と表記されることもあります。
特徴は、顔を白く塗り、コミカルなメイクや動きで観客を笑わせ盛り上げること。しかし、単なる道化役ではなく、隊列を整える、演舞の指示を出す、場を統率するなど、エイサーをスムーズに進める重要なリーダー役を担っています。経験豊富な年長者が務めることが多い、尊敬される存在です。
エイサーの特徴をわかりやすく解説!

何のために踊られる?エイサーの目的
沖縄のエイサーは、旧盆の時期に踊られる先祖供養のための伝統芸能です。
その最大の目的は、お盆に一時的に戻ってきたご先祖様の霊をあの世へ無事に送り届ける「精霊(しょうろう)送り」の儀式を行うことです。起源は本土から伝わった念仏踊りにあります。
また、各地域の青年たちが家々を回る道ジュネーでは、厄払いや地域の平穏と繁栄を祈願する意味も込められており、共同体の絆を深める重要な役割も担っています。
エイサーの太鼓の種類
エイサーで使われる太鼓は3種類あります。

大太鼓は肩から下げ、低い音を力強く響かせます。
重量もあるので、体の大きな男性がやっていることが多いです。
締太鼓は主に左手に持ち、右手のバチで叩きます。
大太鼓より素早い動きや、細かい動きが得意となります。

パーランクーは、締太鼓と同じく片手で持ちます。タンバリンのように小さく軽いのが特徴です。
軽くて子どもでも扱いやすいので、小学校の運動会でも取り入れられたりします。
パーランクーで有名なエイサーと言えば、うるま市の平敷屋青年会が有名です。平敷屋青年会は、衣装なども独特で、古い形のエイサー(念仏踊り)に一番近いと言われています。
なんとなく、お坊さんに見えなくもない!?
エイサーの分類(種類)
エイサーの分類と言う種類分けが正しいのか分かりませんが、ザックリ大きく分けると2つに分かれます。
沖縄でエイサーと言うと中部が盛んですが、青年会は各地域にあるものなので、那覇とかでも青年会でエイサーをやってるいるところはあります。
青年会のエイサーはイベントで踊られたりもしますが、旧盆に各地域で踊ることが最大のイベントになります。
お盆に先祖供養のために踊っているのは、青年会のエイサーになります。
■旗頭:青年会の名前の書かれた3,4mくらいの大きな旗を掲げます
■地謡(じかた):歌三線で民謡のエイサー曲を奏でます
■大太鼓:上記のとおり
■締太鼓:上記のとおり
■手踊り:主に女性ですが男性もあります
■チョンダラー:エイサーの道化師で盛上げ役ですが実はベテラン
有名な青年会だと、園田青年会(沖縄市)や、平敷屋青年会(うるま市)がありますね。
お盆の夜に、地域の中をねり歩き、場所を変えながら演舞をしていきます。
このことを「道ジュネー」と言います。
私はこの道ジュネーの太鼓の音が聴こえてくると、ワサワサしてきて太鼓の音がする方に、自然と引き寄せられます。笑
青年会のエイサーは、本当にカッコよくて推しの青年会を見るために、内地からわざわざ来る追っかけもいるくらいなのです。
創作エイサーは青年会のエイサーから進化したもので、イベントなどで魅せることを主な目的としているエイサーです。エンターテイメントとしての要素が強い踊りになります。県外のエイサー団体やサークルもこちらの分類になりますね。
こちらをエイサーと呼ぶのに異論を唱える人もいるようですが、私個人としては創作エイサーも立派に確立していると思います。
創作エイサーの曲は、三線の民謡もあればポップスを使っているところもあり形態は様々です。
衣装も青年会風なところもあれば、紅型柄を取りいれたオリジナルな衣装だったり、様々な衣装は見ていても楽しめます。
団体によっては女性や子どもも太鼓を叩いていたり、各団体が自由に活動しています。
見ていて華やかなのは、創作系のエイサーかも知れませんね。
創作エイサーで代表的なのは、琉球國祭り太鼓(動画)が有名ですね。
また、沖縄で創作系のエイサーが見たい方は、おきなわワールドではいつでもエイサーのショーを楽しむことができますよ。
アソビューならおきなわワールドの入場料も割引に♪エイサーの歴史を分かりやすく解説まとめ
以上、沖縄のエイサーの歴史と特徴についての基本を簡単に紹介しました。
エイサーは、単なるお祭りではなく、袋中上人が伝えた念仏踊りを起源とする先祖供養の行事です。太鼓の力強い響きやチョンダラーの道化役は、ご先祖様への感謝と地域の繁栄を願う、沖縄の人々の魂そのものを伝えています。
この記事を通してエイサーの奥深い歴史と特徴を知ることで、次に演舞を鑑賞する際は、より深い感動を味わえるでしょう。ぜひ、沖縄の文化と情熱を感じてください!