今回は沖縄の伝統工芸品「琉球漆器の特徴」について紹介します。
あなたは、琉球漆器を知っていますか?
漆器だと石川県の輪島塗などが有名ですよね。
ですが、沖縄にもあるんです!世界に誇れる琉球漆器が。
今は焼失してしまった首里城ですが、首里城は「大きな琉球漆器」とも言われているんですよ。
今回の記事は、その琉球漆器の特徴と琉球漆器にまつわる個人的エピソードの紹介です。
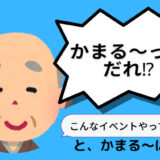 沖縄の童名(わらびなー)と沖縄のおじぃについて
沖縄の童名(わらびなー)と沖縄のおじぃについて
【この記事で分かること】
■琉球漆器の基本
■琉球漆器の特徴
■琉球漆器の主な種類
この記事は沖縄生活13年、沖縄では歴史サークルに所属していたももとが書いています。
\楽天トラベルなら楽天ポイントが貯まります/
\沖縄の宿を予約する/
(公式サイトに移動します)
沖縄の琉球漆器の特徴
琉球漆器は沖縄で作られている漆器で、14~15世紀頃に中国から伝わったとされています。
高温多湿の沖縄は、漆器を作るのに適した気候でもありました。
琉球漆器の特徴は、とにかく加飾技法が多いことです。
加飾技法とは金箔を貼ったり装飾することだよ
琉球漆器の代表的な3つの技法を紹介すると以下の通りです。
①堆錦(ついきん)
②螺鈿(らでん)
③沈金(ちんきん)
本当は他にもたくさんあるのですが、まずはこの3つさえ押さえておけば大丈夫です。
この3つが言えるだけでも「琉球漆器に詳しい人」認定されるよ
文字で見てもなんのこと?と思うので、早速画像付きで紹介しますね。
①琉球漆器の技法 堆錦(ついきん)

堆錦(ついきん)は、中国の「堆朱(ついしゅ)」という技法から、沖縄独自の変化を遂げ完成した技法です。
漆に顔料を練り混ぜて「堆錦餅(ついきんもち)」というものを作り、それを薄く伸ばして模様を切り取ります。
切り取った模様を器の表面に貼り付け、立体的な模様を表現します。
②琉球漆器の技法 螺鈿(らでん)

螺鈿(らでん)は、夜光貝や蝶貝など光沢のある貝殻を薄く削って模様に合わせて切り抜き、その貝殻を漆で貼り付けたり埋め込んだりする技法です。
私は以前、この螺鈿でつくられたつい立のようなものを、北海道の赤レンガ庁舎にあった博物館で見たことがあります。
詳細は忘れてしまいましたが、過去に沖縄から北海道に贈られたもののようでした。
③琉球漆器の技法 沈金(ちんきん)
沈金(ちんきん)は、漆を塗った表面に沈金刀を使って模様を彫り、彫った模様に生漆を摺り込み、乾燥する前に金粉や金箔を押し込んで乾燥させます。
最後に余分な金粉などを拭き取ると絵柄が現れるという技法です。
琉球漆器の沈金体験会に行ってみる
さて、琉球漆器の特徴はこのくらいにして、かまる~おじぃとのエピソードの紹介です。
かまる~おじぃとは、沖縄での職場にいたおじぃで、お祭りやイベントがあるといつも私を誘ってくるおじぃです。
そのお誘いを10回中9回は断っているのですが、この時は私も興味がある内容だったので、かまる~おじぃの誘いに乗ることにしました。
そのイベントの内容は、首里城でやってる「琉球漆器の沈金体験」というもの。
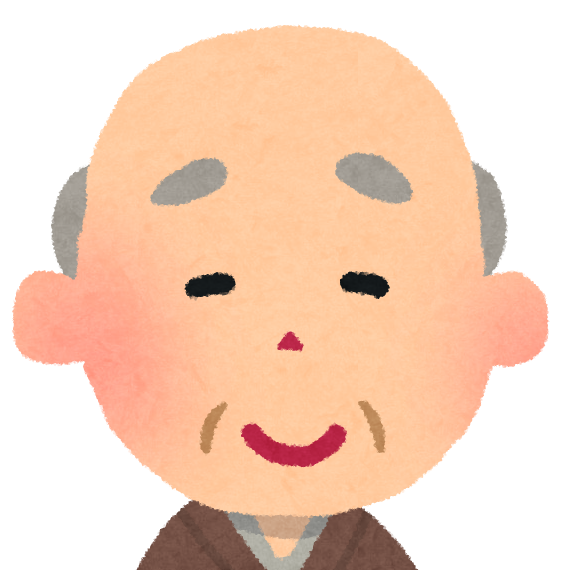
ももとさん、こんなイベントあるよ
面白そうですね~行きます
首里城でやっていると言いましたが、正確には首里城公園内にある建物の会議室のようなところで開催されていました。
イベント当日、かまる~と待ち合わせ首里城へ向かい、会場に入ると、
なんか子どもが多い??
よく見ると、小学生の子どもとその親の組み合わせで来ている人ばかりでした。
いや、うちらも親子くらい歳が離れてる組み合わせだけど・・・
これって夏休みの自由研究じゃん!(-_-;)
そう、世間は夏休みでした(^^;
その体験ワークショップは、子ども限定とは書いていないものの、明らかに夏休みの子どもを対象にしているイベントでした(^^;
こんな歳を取った親子(じゃないけど)でも受け入れてもらえたので、小学生に混じって沈金体験をやりましたよ。
体験自体は面白かったのですが、ちゃんと内容確認してよ~ですよね(-_-;)
琉球漆器の特徴まとめ
琉球漆器って全国的にはあまり知られていませんが、沖縄の素晴らしい伝統工芸品のひとつです。
琉球王国時代には、他国への重要な献上品でもあり、漆器を作る部署である「貝摺奉行所(かいずりぶぎょうしょ)」が設置されていました。
そんな歴史ある琉球漆器について、今回は本当にさわりだけの紹介でしたが、もっと詳しく知りたいと言う方は、ぜひ浦添市美術館に行ってみてください。
浦添市美術館は、琉球漆器を常設展示をしている美術館です。
沖縄って小さな島だけど、世界に誇れる文化がたくさんあって本当に素晴らしいですよね。
今回はそんな中のひとつ、琉球漆器の紹介でした。
\最後まで読んでいただきありがとうございます。クリックしていただけると励みになります/






こんばんは
いつもわかりやすく興味深い記事をありがとうございます
漆器の技術の広まり方と沖縄での成熟さなど
考えるとロマンがありますね
次回も楽しみにしています
がんばって!!
まりんさん
コメントありがとうございます✨
最近Twitterの方、お休みされてるようで心配してました〜
琉球漆器、あまり知られてないので、少しでも多くの人に知って欲しいです☺️
まりんさんのお陰で、また頑張ろうって思いました😆
ありがとうございました😊